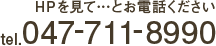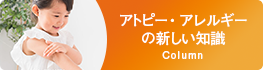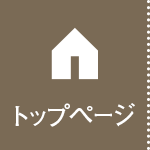「アレルギーで悩む人々を笑顔にしちゃうプロジェクト☆」で日本を元気に。
千葉県松戸市でアラテックセラピーが受けられるのは、てんびん鍼灸治療院だけです。
Contents
〜女性ホルモンのゆらぎと、体質の関係を知る〜
「生理前になると鼻炎がひどくなる」 「皮膚の痒みや蕁麻疹が悪化する」 「花粉症の薬が効きにくい気がする」 そんな経験はないでしょうか?
実は、アレルギーと生理周期というのは女性ホルモンの変化を通じて密接に関係しています。
さらに東洋医学の観点から見ると、「体質」と「ホルモンの波」が重なって症状が現れているケースも多かったりするのです。
生理前にアレルギーが悪化しやすい理由
女性の体は、1ヶ月の中でホルモンが大きく揺れ動きます。 生理前(排卵後〜月経直前)は、黄体ホルモン(プロゲステロン)が優位になる時期です。
プロゲステロンは、妊娠に備えるために体内の水分や熱をため込みやすくする作用があります。
その一方で、
- 炎症を助長する
- ヒスタミン反応を強める
- 粘膜をむくませる
といった免疫面への影響もあり、花粉症・鼻炎・蕁麻疹・皮膚炎といったアレルギー症状が悪化しやすくなります。
よくある症状の変化
- 鼻づまりやくしゃみが強くなる
- 花粉症・ハウスダスト症状の悪化
- 皮膚のかゆみや赤みが増す
- 食物アレルギーや過敏反応が強く出る
- 蕁麻疹の頻度が増える
ホルモンバランスの変化は目に見えませんが、体の免疫反応には確実に影響を与えています。
東洋医学から見た「アレルギーと生理」
東洋医学では、生理やホルモンのゆらぎとアレルギーの背景に、「血(けつ)」「肝(かん)」「脾(ひ)」という3つの要素が深く関係していると考えられています。
● 血虚(けっきょ)タイプ → 「血」が不足し、皮膚や粘膜のバリアが弱っている状態。 乾燥・かゆみ・炎症が出やすく、生理量が少ない、顔色が青白いといった傾向があります。血が不足していると、ホルモン変化の影響を受けやすく、アレルギー症状が強まります。 養生のポイント:黒豆、なつめ、レバー、ほうれん草など「血を養う」食材を意識しましょう。
● 肝鬱(かんうつ)タイプ → 「肝」は自律神経や情緒のコントロールと深く関わる臓腑。 ストレスやイライラで「気(き)」や「血(けつ)」の流れが滞ると、鼻炎や蕁麻疹が悪化しやすくなります。生理前は情緒が不安定になりやすく、このタイプでは特に症状が出やすい傾向です。 養生のポイント:しそ、みかんの皮(陳皮)、ジャスミン茶など香りの良いものを取り入れ、リラックスを意識しましょう。
● 脾虚(ひきょ)タイプ → 「脾」は西洋医学でいう“消化・吸収・免疫”の働きに近く、体の「気・血・津液(体液)」を生み出す土台です。
脾が弱ると、
- 栄養をうまく吸収できない
- 余分な水分(湿)が体にたまりやすくなる
- 免疫のバランスが崩れやすくなる
といった状態になります。この「湿」が鼻水・痰・鼻づまり・皮膚のジュクジュク感など、アレルギー症状の悪化に深く関係します。
さらに、脾の弱りは血の生成やホルモンリズムにも影響し、生理前の揺らぎが強くなる要因にもなります。
養生のポイント:冷たいものや甘いもの・脂っこいものを控え、はと麦、山芋、とうもろこし、きのこ類など、脾を補い湿をさばく食材を取り入れるとよいでしょう。
生理前の悪化をやわらげる生活の工夫
- 体を冷やさない → 冷えは湿と炎症を助長します。温かい飲み物や入浴で巡りを整えましょう。
- 睡眠とストレスを整える → 自律神経と肝のバランスが整い、ホルモン変化の影響も和らぎます。
- 腸内環境を整える → 脾の働きを助け、免疫の過剰反応を抑えます。味噌・納豆・ヨーグルトなどの発酵食品が◎。
- 食事で炎症を抑える → 青魚(EPA・DHA)、亜麻仁油、えごま油、抗酸化野菜を日常的に取り入れましょう。
生理前にアレルギーが悪化するのは、ホルモンの自然な変化と体質の組み合わせによるものです。
ホルモンは変えられませんが、「体の受け皿(体質)」を整えることで、影響をやわらげることは十分可能です。
- 血(けつ)を養う
- 肝(かん)をなだめる
- 脾(ひ)を元気にする
この3つを意識することで、アレルギーと生理のゆらぎが少しずつ穏やかになっていきますよ。
体質改善のアドバイス
それでは「血」「肝」「脾」を自分で整えていく具体的な方法を確認してみましょう。
- 血を養う:血は身体や心を滋養する土台です。血が足りない(血虚)と、貧血・冷え・不眠・肌の乾燥・月経不順・集中力の低下などが現れてきます。
◇食事=赤~黒で甘みや酸味を持つような食材がおススメ
例)黒ごま、なつめ、クコの実、レバー、ほうれん草、にんじん、黒豆、プルーン、ブドウ、桑の実、鶏卵、卵黄
鉄分+たんぱく質+ビタミンCをセットで摂るようにする→血を作る材料の吸収を高める組み合わせになる
◇生活=夜更かしを避け、0:00前には就寝する→血は夜に肝で作られるため
月経後・出産後はしっかり休む・温める→血が消耗されやすい時期は、積極的に「補う」こと
深呼吸や軽いストレッチで血流促進→呼吸は「血の巡り」を助けます - 肝をなだめる:肝は「気血の流れ」をコントロールし、情緒や自律神経にも関係します。ストレス・怒り・緊張で肝の働きが滞ると、気鬱・月経不順・頭痛・肩こり・不眠などが生じます。
◇食事:香りの良い緑の食材がおススメ
例)セロリ、春菊、しそ、ミント、柑橘類、玉ねぎ、ねぎ、生姜
脂っこい・刺激物・アルコールの摂り過ぎを避ける→肝の解毒・代謝作用の負担になります。
酸味を適度に摂る
例)梅干し、黒酢、レモン→肝気の流れを整える
◇生活:感情を抑えすぎず、こまめに発散をする→散歩・深呼吸・好きな音楽を聴く・自然に触れるなど
春は特に「肝」が高ぶる時期→ストレッチや軽い運動で「気」を動かす(巡らせる)
目の酷使を控える→肝は「目」に通じるため、スマホやPCの長時間使用は控えめに - 脾を元気にする:脾は「消化吸収」や「気血の生成」に関わる中心。脾が弱ると、食欲不振・疲れやすい・むくみ・下痢・痩せにくい・思考の鈍りなどが現れます。
◇食事:温かく、淡味*のある穀類や根菜を中心に *淡味=あっさりしていて濃くない・自然な薄味のこと
例)米(特に玄米・雑穀)、かぼちゃ、さつまいも、にんじん、大根、山芋
冷たいもの・生もの・甘いものの摂りすぎを控える→脾胃を冷やすと消化が停滞する
「噛む回数」を増やす→脾の働きを助け、気血の生成力がが高まる
◇生活:朝食を抜かない→脾は午前中に活性化します
考えすぎ・心配しすぎに注意→思慮過多は脾を傷める
軽い運動・腹式呼吸で代謝を整える→特にウォーキングや太極拳などリズム運動は良い
自分(家庭)でできるツボ療法
生理やアレルギー症状は、日々のセルフケアでやわらげることもできます。
鍼灸治療では施術を通じて「気・血・水の巡り」を整え、体質を穏やかにしていくように働きかけていきます。
ここではご家庭でもできるツボ押し・お灸ポイントを紹介します。
⸻
 三陰交(さんいんこう)
三陰交(さんいんこう)
足の内くるぶしの上、指4本分のところ。脛の骨際で比較的ツンとした刺激の出やすい場所になります。
生理痛、冷え、むくみ、ホルモンバランスの乱れによく使われる代表的なツボです。
ケア方法:
・指先で3〜5秒押して離すを5回ほど繰り返す
・夜の入浴後や寝る前に温める(市販のせんねん灸などもOK)
⸻
 太衝(たいしょう)
太衝(たいしょう)
足の甲、親指と人差し指の骨の交わる手前のくぼみ。
「肝(かん)」の巡りを整え、イライラ・情緒不安定・アレルギー反応の過敏さを鎮めるツボです。
ケア方法:
・軽く押してズーンと響く感じがするところを中心に刺激
・深呼吸しながら5回ほど押し、吐く息に合わせて力を抜く
⸻
 曲池(きょくち)
曲池(きょくち)
肘を曲げた時にできるシワの外側のくぼみ。
皮膚のかゆみ・炎症・アトピー性皮膚炎・蕁麻疹などに効果が期待できます。
ケア方法:
・反対の手の親指でゆっくり円を描くように押す
・お風呂上がりなど、体が温まった時に行うと◎
⸻
ツボ療法のポイント
・強く押しすぎない
・「心地よい刺激」を目安にする
・左右とも行ってOK
・継続することで体質改善をサポートします
⸻
アレルギーも生理も、ホルモンと免疫・自律神経のバランスが整うことで驚くほど変化していきます。コツコツと継続して取り組まれてください。
てんびん鍼灸治療院では、体質そのものを見直し、東洋医学の知恵とアラテックセラピーを併用することで、より健やかな毎日へ導けられるようにお手伝いをいたします。
アラテックセラピーは心身に形成された誤反応を見つけ出し、元通りに修正していく施術法です
アレルギーでも過敏症でもその根っこは同じ、身体システムのどこかにエラー反応(誤認識)が形成されてしまっていることで様々な不調が現れます。
アラテックセラピーは、それらエラー反応を見つけだし、エラー反応が起こる前の状態、即ち心身と物質や刺激との元通りの関係性へとリセットさせていく施術法になります。
生理に関わるお悩みに対しては、ホルモンへの働きかけや、食品群(個人差有り)へのエラー反応の修正などで、生理痛や周期異常のコントロールが行えることもあります。

アラテックセラピー
各種アレルギーや過敏症でお悩みの方、この治療法に興味を持たれた方は、以下の関連ページもご覧ください⇩