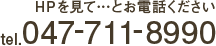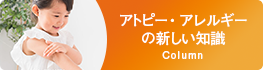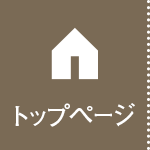「アレルギーで悩む人々を笑顔にしちゃうプロジェクト☆」で日本を元気に。
千葉県松戸市でアラテックセラピーが受けられるのは、てんびん鍼灸治療院だけです。

鍼灸院にいらっしゃる方々の中には、日々の食事をはじめとした生き方に自然志向である方が比較的多くいらっしゃいます。
「なるべく薬に頼りたくないんです」という方針もその一つですよね。
そんな中で、ほとんどの方が意識されているのが今日のタイトルにもある添加物や化学調味料。
これらを避けるようにされている方がとても多いと感じます。
今回は添加物(化学調味料)の詳細と、最近目にすることも増えてきた飲食店の「無添加」「無化調」の意味や、それらの健康への影響を交えながら説明します。
当然これらの物質にアレルギーや過敏症を持たれている方も存在します!
そちらが気になる方は⇊の関連リンクもご参照ください。
Contents
食品添加物の特徴
食品添加物とは、食品の品質を保持したり、保存性を向上させたり、風味や見た目を良くする目的で食品に加えられる物質のことを言います。
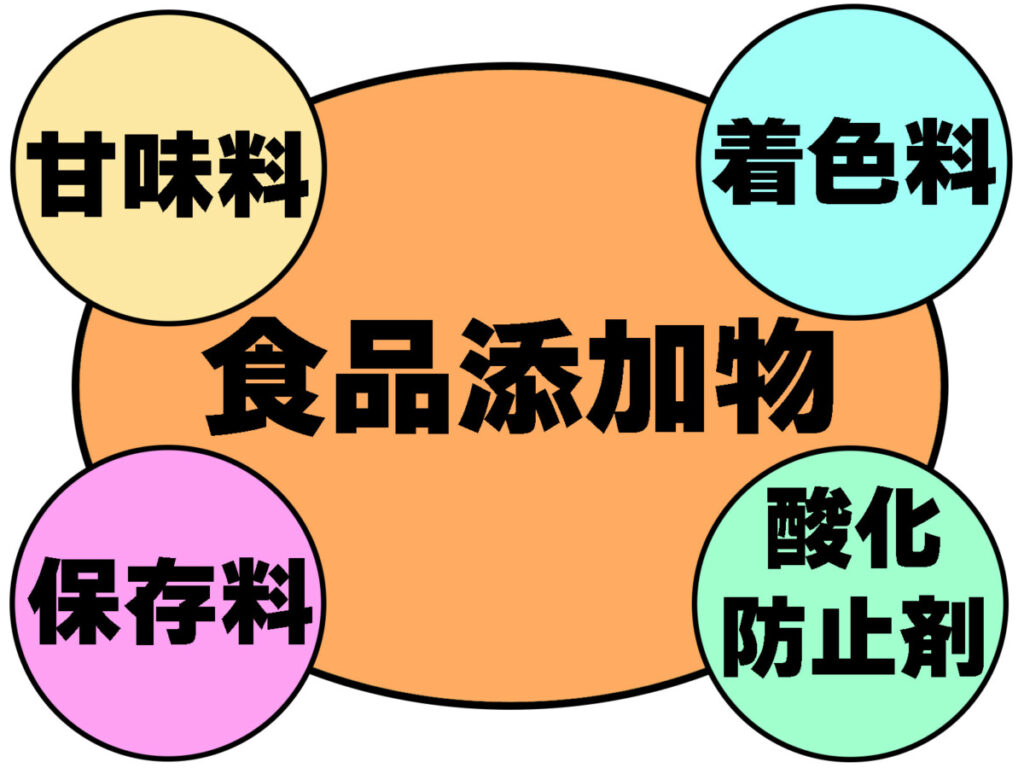
食品添加物には次のような分類があります。
- 保存料:食品が腐らないように添加する
(ソルビン酸、安息香酸ナトリウムなど) - 着色料:食品に色を付けたり、鮮やかさを維持できるように添加する
(赤色〇号、β-カロテンなど) - 甘味料:砂糖の代替として添加する
(アスパルテーム、ステビアなど) - 酸化防止剤:食品の酸化を防ぎ、品質を維持するのに添加する
(アスコルビン酸など) - 増粘剤/ゲル化剤:食品のテクスチャーを整えるのに添加する
(キサンタンガム、寒天など) - 化学調味料:広義では化学調味料も添加物(安全性が確認されている指定添加物)に属します
食品添加物の使用目的

食品添加物は、長期保存や見た目の良さ、製品の均一性を確保するために使用されています。
例えば、加工食品や冷凍食品、ジュース類、お菓子類では保存料が非常に重要な役割を担っています。
食品添加物への誤解
- 「食品添加物は全て人工的で有害」
実際には、食品添加物には天然由来のものも存在します。例えば、〝にがり〟や〝寒天〟などは自然由来の添加物です。
また、食品添加物の安全性は厳密な基準に基づいて評価されており、一般に通常の摂取量では健康に影響を与えないとされています。 - 「食品添加物は体内に蓄積される」
科学的には、食品添加物は体内で分解されるか、排出されるため蓄積されることはありません。
化学物質への不信感からこのような誤解が生じることが多いです。 - 「飲食店の無添加の意味」
最近は健康志向の高まりやニーズに応えて、お店の特徴に「無添加」を標榜する飲食店舗も見られるようになってきました。
さて、この「無添加」の範囲ですが、日本の法律上は統一された明確な基準が存在しないため、実は企業や店舗のポリシー、定義付けによってその詳細が異なる可能性があります。
「無添加」の標榜と一緒に「保存料不使用」「化学調味料不使用」などと謳っているお店は、その無添加の内容をより明確に表していると言えます。
また、畜産肉や養殖魚を扱っている場合、たとえその育成過程で抗生物質や保存料が餌で使われていたとしても、加工や販売の段階で添加物が使われていなければ無添加の食品として扱えると、関連法規によって定められています。

ゆえに過剰な添加物類の摂取はおススメしませんし、身体の解毒・排毒機能を高めたい時などには、余計な添加物類をなるべく摂取しないようにしておくと少しでも肝臓や腎臓の負担を減らして
自然治癒力の発揮を促せるということを知っておきましょう。
化学調味料の特徴
化学調味料は、食品の味を引き立てるために使用される成分で、主に「旨味」を高める役割を果たします。
広義では添加物に含まれるものになりますが、その安全性と消費者の誤解から、その他の添加物とは分けてお伝えします。

自然界に存在するアミノ酸(グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸、コハク酸等)に
ミネラル(金属イオン)を結合させて精製されています。代表的な化学調味料には次のようなものがあります。
- グルタミン酸ナトリウム(MSG):
(旨味を強化する) - イノシン酸ナトリウム:
(肉類や魚介類の旨味を引き立てる) - グアニル酸ナトリウム:
(キノコ類の旨味を増幅させる) - コハク酸ナトリウム:
(シーフード系の旨味を高める)
化学調味料の使用目的
化学調味料とは、自然の食品にも含まれている旨味成分を意図的に製品に加えることにより、強く「美味しい」を感じられるようにするために使用されます。
インスタント食品や加工食品では特に重要な役割を果たしていますし、家庭用の調理サポート製品(〇〇の素)のような製品にはこういった技術の恩恵が詰まっているわけです。
化学調味料への誤解
- 「化学調味料は人工的で危険」
化学調味料(例:MSG)は、現在では発酵技術を用いて天然由来の原料から製造されています*。
化学的な評価に基づき、通常の摂取量であれば健康に悪影響を与えないとされています。 - 「化学調味料は味覚を鈍感にする」
一部の人が濃い味に慣れてしまうことで自然の味付けを薄く感じるようになることがありますが、
これは味覚の変化ではなく、味の慣れによるものになります。 - 「中華料理症候群の原因は化学調味料」
中華料理症候群はMSGが原因と言われていましたが、科学的研究ではその因果関係は証明されていません。
そのため、心理的要因や他の成分の影響があった可能性が高いとされています。
*かつて、グルタミン酸ナトリウム(MSG)は石油由来の化学合成によって製造されていた時期(1970~1980頃まで)がありました。
当時の製造方法は、石油化学製品を原料として化学反応を通じてグルタミン酸を生成するものでしたが、使用されるアクリロニトリルや
強酸、強アルカリなどが製品に残留する可能性や環境汚染、それら化学薬品使用による健康影響の懸念がありました。
当時のMSGは、まさに化学調味料という名が相応しかったと考えられます。
食品添加物と化学調味料の違い
| ポイント | 食品添加物 | 化学調味料 |
| 主な目的 | 保存性、見た目、品質の維持 | 旨味を強化して味を良くする |
| 使用例 | パンの保存料、飴などの着色料 | 即席ラーメンやスナック菓子など |
| 影響 | 長期保存や食品の安全性の確保に寄与 | 美味しさの向上や濃厚な味覚体験を提供 |
| 健康への懸念 | 過敏症やアレルギーの可能性がある | 過剰摂取時に過敏症状や食習慣への影響がある |
健康への影響
現代の一般的な解釈では、食品添加物も化学調味料も、ともに適切な範囲で使用されていれば問題ないとされています。
が過剰摂取や偏った摂取は健康に影響を与える可能性があるため気をつける必要性は出てきます。
- 食品添加物は、一部の保存料や着色料がアレルギー反応や過敏症の原因になる場合があります。
例)
安息香酸ナトリウム:喘息やアトピー性皮膚炎と関わる可能性
パラベン:じんましんや喘息と関わる可能性
亜硫酸塩:喘息と関わる可能性
赤色40号:じんましん、発疹、呼吸困難などと関わる可能性
黄色4号:じんましん、喘息、消化器症状と関わる可能性
コチニール色素:腫れ、喘息、アナフィラキシーなどと関わる可能性 - 化学調味料は、その成分に過敏な人が摂取した場合には「MSG過敏症」と呼ばれる一時的な症状(頭痛、吐き気など)が現れることがあります。
ですが、その主成分であるグルタミン酸は、天然の食品に含まれる成分と化学的に同一のため、過敏症でない方が一般的なレベルで摂取することには影響はありません。

関連記事➡➡グルタミン酸ナトリウム(MSG)過敏症について
食品添加物や化学調味料類に過敏反応があるという自覚があるのなら
特定の物質にアレルギーや過敏症をお持ちの場合には、そういった添加物や化学調味料類を避けたり外食をしないようにする。
というのが一般的な対処法になってくると思います。
実際にそのような方々が一定数おられるわけですが、現実問題としてはかなり不便な生活を強いられることになってしまいます。
・友人や会社の仲間と飲みに行けない
・食品の買い物にいちいち時間がかかる
・口にできるものがかなり限られてしまう
・オーガニック食品等の選択で食費が増えがちになる
・外食の選択肢が狭まってしまう
・料理に手間がかかる
ある程度は妥協ができるのか、厳密に避けねばならない程重篤な症状が現れてしまうのか、
症状レベルによっても差は出てきますが、こういった不都合が発生しているはずです。
そういった煩わしい生活をこれからもずっと続けられるくらいであれば、アラテックセラピーを受けてみませんか?
きっと、食品添加物や化学調味料に対する過敏反応に悩まれているあなたにも、
「ある日を境に急に口にできなくなってしまった」
という実体験があるのだと思います。
アラテックセラピーは、そんなあなたの心身に起こってしまった、身体システムの誤作動状態を、科学的に自律神経の働きにアプローチすることで、
元通りの状態に戻してあげることのできる施術法なのです。
もしあなたがこのような症状でお悩みなのであれば、すぐに一度ご相談ください➡お問い合わせ

アラテックセラピー
各種アレルギーや過敏症でお悩みの方、この治療法に興味を持たれた方は、以下の関連ページもご覧ください⇩